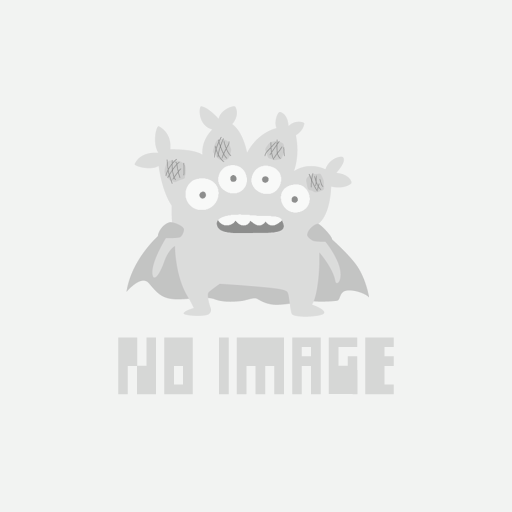八百八郷サイトの方に読み物掲載の形式整えてないので一旦ここに置いておきます
◇
その日の西舌奉行所は大盛況だった。
八百八郷・西地区の中心都市である〈西舌〉。その奉行所は日々、大勢のヒトと化妖とで賑わっている。公的手続きからごみ処理相談、自治組織の任務受注、そして〈化遣衆〉西地区支部の窓口など、対応、対応、様々な対応が行われているのだ。
井正は完全に出遅れた形となっていた。昼を過ぎ、日が天頂より傾きはじめて暫く経った刻である。今日中に事務処理を済ませてほしいなどと告げれば、職員の眉間に深い皺が刻まれること請け合いだろう。
このヒト入りである。内も外もごったがえしになっている。原因は言わずもがな、〈西舌〉に入ってからの道中で散々目にしてきた〈例のあれ〉の影響であろう。
「なあ、ついに、ついにや、明日やで!」
「ああ~!わたし今日は緊張して寝られへんかも…」
「まさか〈三ツ割〉との決着がここまでもつれるとは…」
「泣いても笑っても明日や!」
〈野球〉だ。現在の八百八郷の頂点を決める団体球技。この街・〈西舌〉を本拠とするチーム〈鶴亀レッグス〉はそれなりの強豪であるが、未だ一度も地区優勝を決めたことがない。それが今、眼の前まで迫っているのだ。生まれてから一度も〈優勝〉というものを味わったことのない住民は浮足立っていた。遠方からはるばる駆けつけた者たちの姿も多く見受けられる。奉行所で耳にした話によると、宿泊施設はどこも満員御礼なのだとか。
井正は、まったく間の悪いことだと思った。野球の影響もあってか、奉行所もこの有り様である。〈化遣衆〉西支部への報告書提出についても、確認と承認まで数日かかる見込みだ。
〈化遣衆〉は化妖とヒトを繋ぐ目的で設立された公的機関である。だが、歴の浅いこの組織は目立った実績も少なく、一般的な知名度もまだまだ。西地区支部は独立した事務所体制ではなく、この奉行所を通す形で回っているという。
対応の煩雑さは変わっていないのだな。と……井正は暫し回想した。1年ほど前のことだ。八百八郷探訪のスタート地点としてお爺ちゃんに連れられてやってきたのがこの街であった。当時は――あまりにも大量の〈活きた名〉を短時間に浴び、たちどころに体調を崩してしまったため、島に戻らざるを得なかった。苦々しい記憶だ。
名酔い対策として今回の度は西端から歩を進めたのだが、これは正解だったらしい。少しずつ〈名〉の量を上げていったおかげか、今度はこの街でも酔うことなく――
「(…いや、これでも厳しいか)」
〈西舌〉の街はまだマシだった。街が御納戸茶色に――〈鶴亀レッグス〉応援一色になっていたおかげか、多量多種の〈名〉を目にしにくくなっていたから。だがこの奉行所はよろしくない。ヒトが多すぎる。〈名〉が多すぎる。腹の底から不快の波がせり上がってくるようで、額からも嫌な汗が流れている。
まったく、冗談ではない。この先が思いやられる。井正は柱の陰で俯き目を伏せていた。どれくらい時間が経っただろうか。
「〈化遣衆〉…一丁川井正さん」
ようやっと自身の名を告げられ、受付カウンターに向かう。
しかし、これは予想できていたことだが、書類の確認は明日以降、とのことだった。
…さて、今日も野宿だろうか。そのようなことを思案しながら奉行所を出る。
沙華の様子を見に行くべきか。しかし、己の頭で考えて答えを導き出さねば意味がない。そうでなければ報告書の内容を一部訂正する必要が出てくる。しばらくは合流を避け、一人で本でも読んでいよう。そう考えた井正は腰を落ち着かせる場所を探すべく、再び色鮮やかな街路に足を踏み出した。
◇
「待ちたまえ!そこの君!」
大通りを抜け、やや人の少ない路地に入ったところで、その〈集団〉は現れた。
声をかけてきたのは中心に立つ少年。見た目の年齢は井正と同程度だろうか。井正よりも長い髪をまとめ、かなりの重ね着をしているようで胴体は顔の印象よりも膨らんで見える。
少年の傍らには、少女が二人。大人が三人。皆一様に厚着。八百八郷は未だ秋と言える気候を保っているため、街中では浮いて見えるだろう。
加えて大柄な化妖が一人立っていた。化妖は、相対する化妖の素性を“認識”できる。
「(雪解けの化妖――ならば……)」
「君に聞きたいことがある!」
井正は化妖の正体から状況を類推する。同時に中心にいる少年が、朗々とした調子で話を進める。他の六人は一歩引いた位置から様子を伺っていた。少年は集団で最も高い立場の人物であるようだ。それは本人の態度からも十二分に伝わってくる。衣服でもこもこになった状態でも分かるほど、胸を張りピンと背筋を伸ばして続けた。
「君は以前にもこの街に来ていただろう?その時一緒にいた化妖はどこかね?」
「なんの話だ?」
傍らの化妖の正体、少年の風体、そして何よりこの質問。井正が彼らの正体と目的を察するには十分な情報だった。彼らは井正ではなく、その背後の存在に用があるようだ。
「とぼけるんじゃあない!奴の知り合いなのであろう!」
だが、目の前の少年は〈奴〉と自分がどのような関係にあるかは知らないようだ。
「…? すまないが、心当たりがない」
「本当にこの方なんですか?」
井正がしらばっくれていると、少年の後ろに控えていた少女が口を挟んできた。どうやら、認識を共有しているわけではないらしい。
「う、ううむ……だがこの目立つ髪であるぞ!見間違えようものが…」
「それ、貴方が言います?」
「上等な羽織も見覚えがある!貴族のような佇まいもだ!」
「自己紹介してるんじゃないんですよ」
「あの秀麗なる相貌と瞳を見よ!あんな者が二人も三人もいてなるものか!」
「……それは貴方の方が…」
「? 今なんと申したか?」
「何も言ってません」
…何を見せられているんだ。だが、この少年はかなりはっきりと自分を視認していたらしい。井正は警戒を強めた。
「真に知らぬと申すか?そんなわけがない!少しでも情報が必要なのだよ!なあ君、我々とともに来てはくれぬか?」
少年はまくしたてた。その物言いは応答を待つものではなく、やや急いているように見える。周囲も妙に焦った様子だ。その理由も、井正には見当がついていた。だが、まだ悟らせてはいけない。
「来る…というと、この街のどこかということか?」
「いいや……〈北〉に招待したい」
「ちょっと!それを言っては…!」
どうにもあけすけな性格のようだ。
「北か……すまないが、暇ではなくてな。」
「むぅ………!!」
少年はわざとらしく顎に手を添え、考え込んでしまった。
「だが……だが!――やっと見つけた手がかりなのだ!みすみす逃すことなどあってはならぬ!」
少年は大きな目を見開く。井正は袖の中で煙管を握る。
「ヒト違いれあれば謝罪しよう、だが!!!今は強引にでも連れて…うおッ!?」
少年が言い切るより先に、視界が真っ白に染まる。井正の〈煙〉だ。
井正は低い姿勢で、脱兎が如く駆け出した。井正には力がなければ速さもない。逃げ出すならば、相手が動き出す前に手を打たなければならない。
ひとつ、ふたつ、水の粒が〈西舌〉の街に落ちはじめた。
◇
「はぁ………は…ッ…」
激しい雨粒が背を叩く。立ち入り禁止の工事現場、建造中の橋の下。足場幕の裏に滑り込み、井正はずるりと腰を落とす。日はとうに落ちたが、化学製の街頭は夜道を明るく照らしていた。流石は西の中心地、と言いたいところだが、現在の井正にとっては不都合極まりない。化遣衆の召喚能力も今は使えない。そもそもあれは契約化妖との相互のかけひきである。使える状況ではないのだ。
例の一行から逃げ出して数刻、未だに追いかけっこは続いていた。否、追いかけっこではなく、かくれんぼと表現するのが正しい。
長時間、この雨でも追跡が緩むことがない。井正による〈催眠の煙〉にも適切に対応してきた。少年を中心に統率も取れているようで、荒事慣れが見て取れる。
単純に走り逃げることは不可能。隠れ、探し、移動し、隠れ、探し……それの繰り返しだ。井正は知恵を絞り、どうにか逃げおおせているが、相手の少年をはじめとする数人はそれなりに土地勘もあるようで、完全に撒くことができない。否、ある程度の時間見つからずにやり過ごすことはできた。だが、少年は諦めない。執念と言うべきか。
――やっと見つけた手がかりなのだ!みすみす逃すことなどあってはならぬ!
「(お爺ちゃんから聞いてはいたが、これほどまでとは)」
奴ら〈北の民〉と、井正の後見人との因縁。そのことに思いを馳せる余裕が今はない。如何にして逃げおおせるか。今はそれ以外に割く意識の領域は残っていないのだ。この雨が、疲労が削りとってしまった。
井正はヒトならざる者、化妖ではあるが、身体能力はヒト並みかそれ以下しかない。長時間あちこち駆け回り、緊張の糸を張った状態で、雨によって体力を余計に奪われながら、それでも立ち向かうことなど、できようもない。
―――…………。
意識が遠のく。ここまでの道中にも幾度か厄介な状況に立ち会ってきたが、切り抜けることができていたのは……
「(〈ヤツ〉がこの場にいれば……)」
「…お…らぁ!!」
瞬間、井正の死角から髪の長い少年が飛び出してくる。その手が井正の後頭部を鷲掴み、全体重をかけて押さえつけた。うつ伏せに倒れた井正は少年に、そして同行者の大人二人によって完全に身動きを封じられる。
「……ぐ…ッ」
とはいえ、井正の今の体力では、少年一人であろうと抜け出すことはできないだろうが。
水を吸った長い髪が重く垂れ、止め処なく雫が伝い落ちる。雨音が井正の呻きを掻き消す中、少年はよく通る、張りのある声でこう言った。
「手荒な真似をして申し訳ないと思っているッ!だが……だが我らとて引き下がるわけにはいかないのだ!一族の無念が……家族の、愛する者の命がッ……夢がかかっている!」
「……………」
「私の……渡白河家当主・渡白河丈護の名にかけて!悪いようにはせぬと約束しよう!」
高らかに名を告げるという行為そのものが、井正にとっては“悪い”ことではあるのだが、少年は知る由もない様子だ。
その名はとてつもなく活きていた。力強く存在を示し、発するニンゲンの領域と固く結びついている。独立しきった、強い〈名〉だ。井正の最も苦手とするものだ。臓物の内側から自身の境界が蝕まれるかのような感覚。吐き気、頭痛、耳鳴り、眩暈、平衡の狂い、頭頂から脳が溶け落ちそうな浮遊感。溜まりに溜まった疲労に追加で堆積してきたそれらに押し潰され、井正がまた低く呻く。
「あの化妖に関する情報が欲しい!全てだ!そして君には……奴をおびき寄せる餌になってもらおう!」
「全部言うことないですよ…」
連れの少女が呆れた様子でぼやく。長時間の捕物に付き合ったせいか疲れの色も濃い。
渡白河丈護と名乗った少年の、井正の後頭部を押さえる腕に力が入る。
「さあ、我々と〈北〉へ……ッ!来てもらおうではないか!」
ぱりぱり…かさかさかさ………ばきっ
足元から、周辺一帯から、奇妙な音がした。地鳴りとは違う。何か分厚いものが割れたかのような、乾いた音だ。それは、降りしきる雨の景色には全く似つかわしくない音であった。
「む…?」
違和感に気付いた少年が辺りを見回そうとした。その時だった。
地面がひび割れ、眼前より何かが勢いよく飛び出す。
「とっとと帰るぜババア!!次のおもちゃをこさえねえとなァ!!!」
後の――同行者たちの目撃証言によると、小柄な黒い少年と、白い女性が、地面から飛び出し、空の彼方へ消えていったのだという。二人は雨の中にあって雨に濡れる様子もなく、雨の軌跡を逆行するかのような挙動で、空中を滑りながら飛び去っていった。
奇妙な二人組が出現した“乾いた地面の穴”は、みるみるうちに雨水を吸い込み、どろどろ、ぐっしょりとした――あるべき姿に戻っていく。しかしながら大きく開いた空洞は元に戻ることはなく、自然な重力のまま周辺の植物を、建造中の橋を囲う資材を飲み込んでいった。もちろん、その場にいたヒトと化妖も。
「ジョーゴ!!」
少年に同行していた大柄な化妖が長い腕を伸ばし、その首根っこを掴む。少年はすんでのところで落下を免れた。しかしその腕は、井正の身体を確保し続けることはできなかった。濡れた指先から、ずるりと抜け落ちる。すでに意識を失っているのか、足掻く素振りもない。崩れ落ちた橋桁と同質の物体であるかのように、無機質に大穴へ吸い込まれていく。
「ああっ!奴が!!」
「丈護さん!いけません!!」
それでも少年は“それ”を追いかけようとした。理性を押しのけた、反射の行動だった。傍らの少女が少年の腹にぎゅうとしがみつき、大柄な化妖は暴れる手足を強引に引っ張り返す。
数秒、少年が平静さを取り戻した時には、目の前には深い、闇い空洞だけが広がっていた。地下空間は幾重もの階層構造で構成されているはずだが、全て突き破られているのか、床板が目視できない。手持ちの化学灯をかざしても、その光が何かを照らすことはなかった。
〈西舌〉の…街の構造を知る者なら誰しもが思い至る。この下に広がるものは、その深さは………
「なん…なのだ……?」
〈西舌〉の地下は非常に危険だ。それゆえに、立ち入りは厳重に管理されているし、少し穴を掘った程度で開くようなものではない。だが、目の前にあるものは――……
「丈護さん、あのヒトは諦めましょう。これ以上追いかけてはいけません」
「だが……!」
「あなたの命よりも優先すべきものがありますか!」
少年が押し黙る。
「…彼は、死んだだろうか」
「処理場に落ちたとすれば、助かるはずがありません。化妖ならともかく…」
「アエ……」
「…そうだな 彼は奇妙な化学具を操っていたが、どう見ても普通のヒトだった」
「アノ…………」
大柄な化妖がもじもじとしているが、今の二人にそれを察する余裕はなかった。
「……いいじゃないですか。いい気味ですよ。」
少女は少年の手のひらを見やる。そこには、井正の髪紐が握られていた。
「彼があの化妖の身内なら、どんな顔をするでしょうね。……まあ、わたしたちからすれば、一人や二人じゃ全然足りないくらいですけど。」
「冬芽!!」
少年は空に向かって吠えた。冬芽と呼ばれた少女は、俯きながら目線のみを少年に向ける。
「探しに行くだなんて、言わないでくださいね。明日の便で帰らないと、あなたの方が危ないのです」
「…わかっているさ……だが、この場は捨て置けん。役所に知らせて……それまで、ここにヒトが近づかないよう、見張りを……」
「……外の民などのために、そこまでやらなくても」
少女は己の視界から少年を排し、そう呟く。
「関係あるまい」
「お人好し」
雨は止む気配を見せず、激しい流れは大穴に吸い込まれ、闇に消えた。
◇
“それ”は、直に石畳に打ち付けられることとなった。全身がまるで人形のようにひしゃげ、四肢はぴくりとも動かない。その場で時間を進めているのは、裂けた皮から漏れ出す血液のみ―――
流れる血が突如、蒸発する。否、気体のような物質へと“変化”していく。
ねじれた首の先についている、生気を失った相貌。長い前髪の隙間から除く眼が――突如として見開いた。煙。煙。煙。その眼をはめ込んでいた器が、煙となって気化していく。“彼だったもの”があったその一帯は、一寸先も見えぬほどの白煙で埋め尽くされていった。その眼球を中心にして。
おわり 7話中編につづく